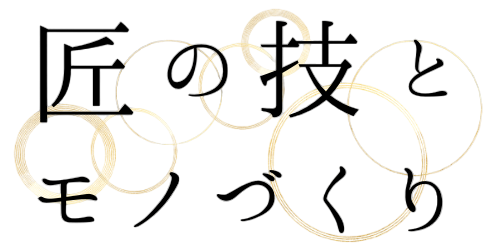日本は地震・台風・豪雨など、世界でも有数の自然災害大国といわれています。いつ起こるかわからない災害に備えるためには、日常生活に欠かせない「防災グッズ」を準備しておくことが重要です。そこで注目されているのが、職人の技術が光る“匠の防災グッズ”です。本記事では、防災グッズの基本から目的、選び方、そして利用者別のポイントに加え、実際に匠の技が込められた具体的な製品についてもご紹介します。
防災グッズとは
防災グッズとは、災害発生時に命や生活を守るための道具や物資を指します。具体的には、飲料水(1人1日3リットル×3日分が目安)、食料(保存がきくものを3日分)、モバイルバッテリー、懐中電灯、ホイッスル、簡易トイレ、救急セット、ラジオ、毛布、現金などが代表的です。これらは被災直後の72時間を乗り切るために欠かせない存在であり、いわば「命をつなぐ道具」です。
また、地震があった時にタンスや食器棚などが倒れないための家具の転倒防止グッズ(突っ張り棒・L型金具)も防災グッズの一つです。
防災グッズの目的
防災グッズの最大の目的は、「災害時の生命を守ること」と「避難生活を少しでも快適にすること」です。
・命を守る
水や食料、応急処置用品は、生き延びるための最低限の備えです。
・安全を確保する
笛や懐中電灯は、自分の存在を知らせたり、暗闇での行動を助けます。
・心の安心を保つ
特に子供や高齢者、女性にとっては、日常と近い状態を保てるグッズが精神的安定に繋がります。
・長期間の生活を支える
避難所生活が長引く場合、衣類や衛生用品の備えが重要になります。
このように、防災グッズは単なる「物」ではなく、命と暮らしを支える“備え”なのです。
匠の技が込められた防災製品紹介
ここでは「匠の技」を活かした具体的な防災アイテムを紹介します。
職人が仕上げた真鍮ホイッスル
災害時に自分の居場所を知らせるホイッスルは、まさに命を守る道具。大量生産のプラスチック製品もありますが、錆びにくい真鍮を使い、職人が一つひとつ削り出して作ったホイッスルは、耐久性・音の響き・デザイン性のすべてに優れています。長く使えるだけでなく、美しい光沢が所有する安心感にもつながります。

和紙加工を活かした防水ケース
日本の伝統素材である和紙は、近年防水加工技術との融合で新たな可能性を広げています。職人が手漉きで仕上げた和紙に防水加工を施したケースは、重要な書類やスマートフォンを守るための防災グッズとして役立ちます。しなやかで軽量、そして自然素材ならではの温かみを感じられるのが魅力です。
手縫いのガーゼハンカチ
乳児や子供、高齢者にとって大切なのが肌にやさしい布製品です。職人が一枚ずつ手縫いしたガーゼタオルは吸水性に優れ、洗っても柔らかさを保ちます。非常時にはタオルとしてだけでなく、簡易包帯や赤ちゃんのおくるみとしても役立ちます。
防災グッズの選び方
防災グッズは「誰が」「どんな状況で」使うかによって必要なものが変わります。ここでは、子供・女性・乳児・ペットといった対象別に選び方のポイントを解説していきます。

子供用
子供用は「安心感」と「軽さ」がポイントです。持ち運びやすいリュック、可愛いデザインの防災ブランケット、柔らかい素材の食器などが安心感を与えます。
女性用
女性用では「衛生」と「プライバシー」が大きなポイントです。生理用品や使い捨て下着、簡易的な仕切りになるポンチョや布などがあると避難生活が快適になります。
乳児用
乳児には「命をつなぐグッズ」と「親の負担を軽減するグッズ」が必須です。粉ミルクや離乳食、哺乳瓶、紙おむつ、おしりふきは最低限必要です。
ペット用
ペットも大切な家族の一員です。ドッグフードやキャットフード、水飲み容器、リードやケージが必需品です。ペットの安心感を守る毛布やクッションも備えておくと良いでしょう。

まとめ
防災グッズは、単に数を揃えることが目的ではなく、「実際に使えるかどうか」が重要です。大人・子供・女性・乳児・ペットと、それぞれの立場に応じたグッズを選ぶことで、非常時にも心強い備えとなります。今一度、防災グッズを見直し、家族や大切な存在を守る準備を整えてみてはいかがでしょうか。