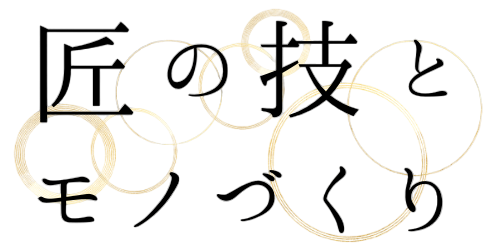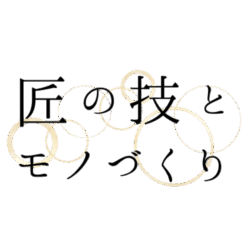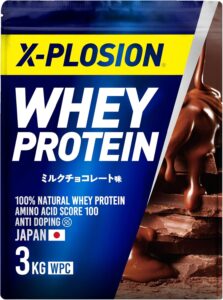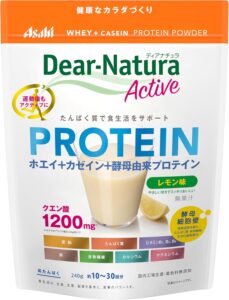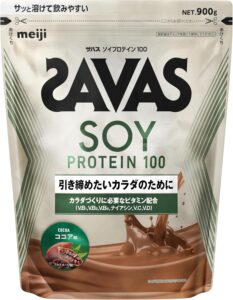日々の健康づくりや理想の体を目指してトレーニングを始める人は増えています。しかし、「自己流でやっているのに効果が出ない」「続かない」「フォームが合っているかわからない」など、悩みを抱える人も少なくありません。そこで注目されているのが、専門トレーナーがマンツーマンで指導するパーソナルトレーニングです。本記事では、自己流との違いや実際にどのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説していきます。
パーソナルトレーニングとは?
パーソナルトレーニングは、トレーナーが利用者一人ひとりの体質・目的・運動経験に合わせて、最適なトレーニングメニューを組み、マンツーマンで指導するサービスです。最大の特徴は「効率的に結果を出せる環境」が整っていることです。
特に、正しいフォームの習得や負荷設定は、トレーニング効果を大きく左右します。自己流では気づきにくい姿勢のクセも、専門トレーナーならその場で修正してくれます。無駄な動きをなくすことで、短期間でも効果を感じやすくなる点は、パーソナルトレーニングの大きな魅力です。

自己流トレーニングで起こりがちな失敗
自己流で頑張っている方も多いですが、意外と失敗が多いのが現実です。
効果が出るまでに時間がかかる
メニュー選びややり方を誤ると、トレーニングの効果が現れにくくなります。筋肉にしっかり刺激が入っていないケースはよくあるパターンです。
フォームが間違っていてケガの原因になる
スクワットやデッドリフトなど、基本動作でもフォームが崩れると腰・膝を痛めることがあります。自己流で続けると、このリスクが非常に高くなります。
モチベーションを継続できない
一人で続けた場合、結果がすぐに出ないとモチベーションが低下して、数週間で止めてしまうこともよくあります。周囲に正しいアドバイスをしてくれる人がいないと、なおさら挫折しやすくなります。
パーソナルトレーニングのメリット・デメリット
メリット1:短期間で効果が出やすい
その人の目的に合わせたトレーニングメニューを提供してもらえるため、効率的に筋肉へ刺激を与えられます。その結果、自己流よりも短期間で体の変化を感じやすくなります。

メリット2:ケガ予防できる正しい動作が身につく
「どこに力を入れるか」「どの角度で動くか」など、細かなポイントを修正してもらえるため、安全にトレーニングできます。
メリット3:食事や生活習慣までサポート
ジムによってはトレーニングメニュー以下にも食事管理や睡眠・生活アドバイスまで対応してくれます。ダイエットやボディメイクでは非常に効果的です。
メリット4:モチベーションを継続できる環境が整う
身体がきついとき、モチベーションが低い時もマンツーマンで伴走してくれるため、継続率が高く、習慣化しやすいのも大きなメリットです。
デメリット1:料金が高い
マンツーマンで対応してくれるため、一般的なジムに比べると料金が高い傾向にあります。近年は低料金で利用できるサブスクのジムも増えているので、目的に合わせてジムを選択するようにしましょう。
デメリット2:トレーナーとの相性
トレーナーとマンツーマンで指導してもらえるのが大きな魅力の一つですが、相性が合わないと長続きしなかったり、不満を抱えたままトレーニングを続けることになります。トレーナーとの関係性に不安がある時は、ジムに相談してみてください。
パーソナルジムを選ぶ際のポイント
パーソナルジムを検索すると、特徴や料金などさまざまなジムがあります。どこを選んでいいか迷うと思います。ジムを選ぶ前に、まずは「何ためにジムに通うのか目的(ダイエット、健康増進、ボディメイク等)をはっきりさせておくことが大切です。
そのうえで、「トレーナーの資格や経歴」「トレーニング内容・料金・回数」「食事指導の有無」「通いやすい立地」「無料カウンセリングの内容」など、さまざまな要素を検討することで、自分に合ったジムを選びやすくなります。
まとめ
自己流でもトレーニングはできますが、正しいフォームや負荷設定が難しく、効果が出にくかったりケガのリスクが高くなります。一方、パーソナルトレーニングはマンツーマン指導で効率的に進めることができ、短期間で結果を出しやすい点が最大のメリットです。効率よく成果を出したい人、安全に運動したい人、なかなか続かない人は、パーソナルトレーニングを取り入れることで、理想の体づくりへの近道になるでしょう。